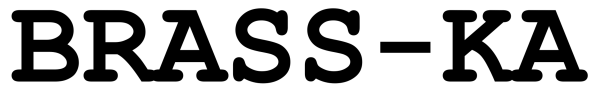大学生が「就職活動」を意識し始めるタイミングは、年々早まっています。
かつては4年生の春からが一般的だった就活も、
今では1年生のうちからガイダンスに参加し、準備を始める学生も珍しくありません。
「スタートラインにも立っていないうちから『動き出さなきゃ…!』という空気の中に放り込まれている。
——そんな感覚を持つ学生が多いんです」
そう話すのは、大学生のキャリア支援に携わる佐藤菜摘さん。
日々、学生たちと向き合う中で見えてきた、就活のリアルについて話を聞きました。

“動き出し”が早すぎて、立ち止まる時間がない
最近では、大学に入学して間もなく、就活サイトへの登録を勧められたり、
複数の就活アプリを入れるよう促されたりする学生も少なくありません。
佐藤さんは「自分が何に興味があるのかすら分からない時期に、就活が始まってしまうんです」と話します。
その背景には、大学側の事情もあります。
就職率の向上が求められるなか、キャリアガイダンスの早期実施や制度的な支援が年々強化されているのです。
「“自分がどうしたいか”よりも、“どう動けばいいか”を先に教え込まれてしまう。
その結果、言われた通りに準備してきた学生ほど、面接で『あなたは何がしたいの?』と聞かれたときに、
自分の言葉でうまく答えられなくなるんです」
「就活」が大学生活の主軸になってしまっている
かつての大学生活は、もっと自由な時間に満ちていました。
アルバイトやサークルに打ち込んだり、旅に出たり。
失敗を重ねながら「自分とは何か」を考える時間でもあったはずです。
「でも今は、大学生活の中心に“就活”が置かれてしまっている。
やりたいことを試す前に『就活のために』と動かざるを得ない状況に、
無自覚のうちに追い込まれてしまっている学生が多いんです」
本来、大学生活は“自分の意思で動ける”貴重な時間です。
しかし「就活のために」という目的が先に立ってしまうことで、自然な好奇心や挑戦心がかき消されてしまう。
佐藤さんは、そんな現状に強い危機感を抱いています。
「自分の興味で動いて得た経験は、面接でも自然に話せるし、相手にも伝わりやすいんです。
逆に、“枠に合わせて無理に作った自分”の話は、どこか薄っぺらくなってしまうんです…」
就活は「自分を知る」プロセスのひとつであるべき
佐藤さんがキャリア支援で大切にしているのは、
「自己理解を深めるきっかけ」を学生に持ってもらうことだといいます。
「まずは幅広く社会を知ってほしい。いろんな会社や人と出会う中で、
『自分はどんな風に生きたいのか』『どんな働き方が合っているのか』を少しずつ見つけていけばいいんです」
就活は“評価される自分”をつくる場ではありません。
“本来の自分”を見つけ、それを社会の中でどう活かしていくかを考える機会であってほしい。
——それが、佐藤さんの考えです。
「仕事は人生の大部分を占めるものですよね。
それがつらい時間になってしまったら、すごくもったいない。
だからこそ、就活を“義務”ではなく、“自分の未来を考える機会”にしてほしいんです」
自分らしい未来をつくるために
就活の入り口に立ったとき、はっきりとした目標がなくても焦る必要はありません。
「まずは『ちょっと気になる』『やってみたい』と思ったことに、素直に動いてみることです。
成功でも失敗でも、動いた経験は必ず何かを教えてくれます」と佐藤さんは話します。
「正解は、誰かが教えてくれるものではなく、自分の中から少しずつ見つけていくもの。
だから、就活=“正解探し”ではなく、“自分探し”として捉えてほしい。
そうすれば、きっとその先に、自分らしく働ける未来が待っているはずです」
まずは一歩を踏み出してみよう
興味のある会社の説明会に一つ参加してみる…
友人や家族、先輩に「どんな仕事してるの?」と聞いてみる…
そんな小さな一歩が、あなたの未来を切り開く大切なきっかけになります。
就活はゴールではなく、これから続く長い旅の出発点。
自分らしい働き方や生き方を見つけるための、あなただけの探検のようなものです。
焦らず、少しずつ、自分のペースで進んでいきましょう。